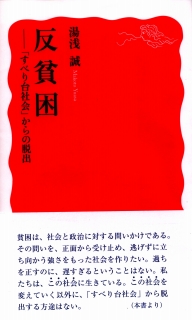埼高教第53回夏期講習会<講座1>
「反貧困~現代の若者の実態と、高校教育に望むこと」(その⑤)
『もやい』事務局長 湯浅誠さん
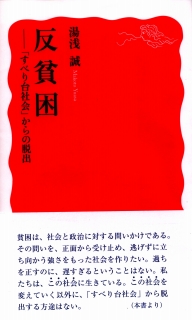
正規と非正規の連携のきっかけを作る
その問題っていうのは、いくら労働市場を見ていても分からないし、労働市場の中だけを見ていると結局、「じゃぁ、正規を削って非正規を増やせば、両者痛み分けで何とかなるでしょう」みたいな、そういう話になっちゃうわけですけど、たぶん正社員の人たち、みなさんもそうかもしれませんけど、日雇いの人から見れば、まだ自分たちは恵まれているなと思っているでしょう?でも、それじゃぁめちゃめちゃ豊かかといったら、もちろんそんな実感ないですよね。だって、教育費とか住宅費とかかかるわけでしょ?子どもにはちゃんとした教育を受けさせたいって、親だったら誰だって思うわけですよ。じゃぁ、自分の給料が減っていくということは、「子供に教育を受けさせるな」ということなのかと、いうふうに感じ取れば、そりぁ正社員の人の抵抗はやたら強くなりますよ。そうなれば「正規」対「非正規」みたいないがみ合いが結局続いていくわけだけども、そこでいがみ合っていても解決策は出てこない以上は、その問題をじゃぁ、稼がないとやっていけないこの高コスト体質をどうするのかというところで、もう一つ連帯の、連携のきっかけを作るという工夫が必要なんじゃないかと、私は思っています。そうじゃないと何度も繰り返し言っているように、「ノーと言えない労働者」がキーキー言い出しているというわけです。日本の労働問題を考えるときには、やっぱりこのノーと言えない労働者っていうのがキーワードだと思いますね。個人としてもノーと言えないし、組合としてもストライキを打てない。ストライキを打てないっていうのはノーと言えないことの典型ですから。働くということを拒否しない。常に働き続けないといけない。日本の消費者というのはボイコットをやらないですから、買わないという選択肢を取らない。これもノーと言わない消費者なんです。つまり日本というのは「ノーと言えない労働者」と、「ノーと言えない消費者」で作られてますから、どうしても運動的に弱くなる。これをどうやってノーと言える労働者と、ノーと言える消費者にしていくのかということが運動の課題になるだろうと思います。
非正規の人たちほど職業訓練も自己啓発もできない
社会保障のデータを見てみると、社会保障費のGDP比が、諸外国に比べて極端に低いということがはっきりします。日本は17.4%です。ドイツが37%、アメリカでも19%、イギリスは29%、フランスは41%ということになってますので、社会保障にかけるお金が全然違う。ということと、あともう一つここで強調しておきたいのは、日本はその少ない社会保障費のほとんどを「医療と年金」だけに使っているので、福祉やその他にまわされるお金が極端に低いんです。ドイツの1/10です。ここに、たとえば職業訓練費用、雇用保険、生活保護、そういうのが全部はいってくるわけです。それが極端に低いということは、つまりそのネットがいかに弱いかということです。いかに労働市場の外で食っていけないかということです。先ほども出てきた「就業構造基本調査」でも、パートやアルバイトのような非正規の人たちほど職業訓練をして新しいスキルを身につけて、労働市場に再参入していく必要が高いのですが、実際にはそういう人たちほど職業訓練も自己啓発もできていない、そういう機会がないということがデータで表れています。そうなれば固定化していってしまうのは間違いない。
日本の労働市場に対する「思いこみ」
私は学校の先生たちに今日二つ目のお願いをしますと、社会に出たら働くもんだというのはいいのですけど、でもそれをもうちょっと相対化する視点を一緒に出していただきたいと思うんです。日本の労働市場に対する信頼、これは信仰といった方がいいと思いますが、これは恐ろしいものがあると思うんです。日本の労働市場というのは人を、常に、全員、食わせるに足るものを提供しているはずだという信念です。なので、働けない人はしょうがないけど、働ける人は、労働市場は常にそれを提供しているはずなんだから、もしお前が働けない、もしくは働いても食べていけないというのなら、労働市場の方に問題があるはずはないので、それはきっと君に問題があるんだ、という話の構成に必ずなってくるんです。だからワーキングプアの「自己責任論」って恐ろしく高いんです。それは、労働市場っていうのは常にそれだけのものを提供してるはずなんだっていう思いこみを、日本社会っていうのはまだ捨ててないんです。これまでそういう時代は一度もなかったと思うんですけど、かつてからそういう神話はあったし、崩れてきたけど、まだ生き残っているという状態にあると思うんです。なので、労働市場は必ずしもあなたの生活を全部は面倒見てくれないんだよ、食えないということはいくらでもあって、それはあんたが悪いんじゃなくてもともと労働市場というのはそんな完全無欠のものじゃないんだよ。だからそういうときは他のもので合わせて、失業保険受けながらとか、生活保護を受けながらとか、足りない部分を補ってもらいながらやっていって、それで別におかしいことじゃないんだよと、いうことをやはり伝えてほしいと思うんです。そうじゃないと、働いてないやつは人間じゃないみたいな感じで、野宿者襲撃みたいなことが後を絶たない。あれはやっぱり、そういった狭い労働観念がいくらか影響している面があると思います。働けるはずなのに、まだ40なのに、50なのに、30なのに、働かずに路上で寝ているようなやつ、こんなやつは社会に何の役にも立ってないんだと、障害者でも高齢者でもないんだから、かわいそうな人でもないんだと、なのでそんなのはやっちゃっていいんだと。そういうイメージを若い人は持ってますけど、それは社会が働く人に対して非常にシビアな社会、働けるんだったら働け、四の五の言うなというような社会だからだと思うんです。
貧困問題を貧困問題だけで見ていてはダメ
そういう状態だということで、労働市場と社会保障全体をみてきましたが、そうなると結局、日本社会の形が変わってきたということになります。かつて日本は提灯型社会といわれていたわけです。つまり中間層が多くて、上下の格差が小さい。そういう意味で提灯型社会といわれていたわけですが、いまはボールを強く握りつぶしたような、縦長の社会になってきているわけです。その結果、やはり貧困ラインを下回る貧困層の人が増えてきたということになります。ただしここで言っておかなければいけないのは、このように貧困層が増えている社会というのは、決して貧困層だけが増えている社会ではないということです。貧困層が増える社会というのは、中間層が弱まる社会であり、かつ富裕層が増える社会だということです。いま日本で資産1億円以上持っている富裕層は150万人いるそうです。生活保護を受けている人が155万人ですから、ちょうど同じくらい。そしてその数は年々5%ずつ増えているということなので、ちょうど同じように上と下が増え続けているということになります。これがこのまま行けば、このボールをずっと握りつぶしていくとどうなるかというと、ひょうたん型社会ということがありますが、中間層が弱くて、上下に極端に二極化した社会ということです。その途上にいまの日本社会というのはあるわけで、それをこのままボールを握りつぶし続けていくのか、あるいはどこかで止めて逆向きにさせるのか、それをいま社会がまさに問われているということになるわけです。そこでまたひとついいたいのは、今日の話は貧困問題ですけど、貧困の問題というのは貧困の人たちだけに焦点を当てていると見えなくなっちゃうんです。さっきの話と似ていますけど。下の広がった部分だけ見ていると、思い浮かんでくる疑問というのは「なんで増えちゃったんだろう」「この人たちはどういう人なんだろう」「本当に困っている人たちなのか」「本当に支援に値する人たちなのか」「この人たちは本当にはい上がろうと努力しているのだろうか」「昔の人より怠け者になっているんじゃないか」「だらしなくなっているんじゃかないか」「根性がないんじゃないか」「ガッツが足りないんじゃないか」「向上心がないんじゃないか」…そういうような話しか出てこなくなっちゃうんです。結局その思考がはまる程度は、「この人たちは本当に支援に値する人なのか」という質問です。この質問は減点法です。「この人、大変だ大変だといっていると思ったら、こないだパチンコやってるの見た」とか、「あの人野宿してるのにお酒飲んでた。だから野宿になったんだ」とか、そういう減点法でしか見なくなりますから、そうなっていくとこれは結果的に命を値切る言い方になるわけです。「あんたにはこんなとこもある、あんなとこもある、だからしょうがないんだよね」というはなしになって、結局は放置しておくための理屈にしかならなくなっちゃうんですけど、どうしても貧困問題を貧困問題だけで見てるとそうなっちゃうんです。だけど実際には社会の形が変わってきてるという問題ですから、貧困層を減らそうと思ったら中間層が頑張らなきゃいけないんですよ。中間層を増やすために頑張らなきゃいかんのです。そういうふうに、自分たちの回りの問題をやることが、まわりまわってそういう問題につながっていくんだという風な認識が必要だろう、と私は思っています。だから貧困問題に取り組むっていうのは別に野宿の夜回りをやらなきゃ貧困問題をやっていることにはならないとは、私は思わない。そうじゃなくて、たとえばみなさんの職場の環境を改善することもそういう問題につながっていくし、またそういう問題と貧困の問題が分けて論じられない、というか別々の問題として起こっていないというところが、いまの大変さなんだと思います。どっかだけいじれば何とかなるという状態じゃぁないと私は思っています。なので、全体を組み直していかないと行けないと思います。
(to be continued...)
その①に戻る その②に戻る その③に戻る その④に戻る